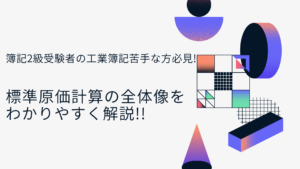企業経営において「コスト管理」は欠かせないテーマです。
その中でも、意思決定やCVP分析(損益分岐点分析)を正しく行うためには、コストを固定費と変動費に分類することが重要になります。

多くの企業は固定費と変動費を大まかに分けるだけで、さらに細かい「原価分解」までは踏み込んでいないのが実態です。
本記事では、管理会計における原価分解の基本的な考え方から、代表的な手法(IE法・最小自乗法・勘定科目精査法など)をわかりやすく解説します。
「固定費と変動費をさらに明確に分類したい方」や「原価分解を初めて学ぶ方」にとって必見の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
- 固定費と変動費をより正確に分類したい経営者・経理担当者
- 原価分解という言葉を初めて聞いた方
- CVP分析を実務に活かしたい方
- 管理会計の基礎を学びたい方
原価分解の種類


原価分解とは、財務会計で計上される費用を、操業度(生産量や稼働率など)との関係に応じて固定費と変動費に分解することを指します。
固定費
- 生産量に関係なく一定額発生する費用(例:家賃、人件費の基本給、減価償却費)
変動費
- 生産量に比例して増減する費用(例:原材料費、出来高払いの人件費、電力代の一部)
財務会計と管理会計の違い
財務会計では「正確な記録」が重視されますが、管理会計では「意思決定に役立つ情報」を得ることが目的です。
管理会計では固定費と変動費の把握が必須であり、場合によっては原価分解を行う必要があるのです。



CVP分析(Cost-Volume-Profit分析)では、売上・費用・利益の関係を把握するために、費用の性質を明確にする必要があります。
原価分解の分類方法


原価分解の方法は大きく分けて2種類あります。
技術的な予測に基づく方法
- 過去データが少ない場合や新製品の導入時に利用される
- 代表例:IE法(工学的方法)
過去の実績データに基づく方法
- 実績を活用して固定費・変動費を推定する
- 代表例:高低点法、スキャッター・チャート法、最小自乗法、勘定科目精査法



それぞれの具体的な手法を解説します。
IE法(工学的方法)
IE法は、作業研究や工学的な分析に基づいてコストを予測する方法です。
従業員の作業時間や原材料の使用量を測定し、それに基づいてコストを見積もります。
メリット
- 新製品や過去データがない場合でも利用可能
- 理論的で説得力がある
デメリット
- 作業とコストの因果関係を正確に捉えるのが難しい
- 専門知識と労力が必要



新製品を製造する際に、試作データや作業分析をもとに、材料費や労務費を予測するケースで活用されます。
高低点法
過去データの中から操業度が最も高い時点と低い時点を結び、固定費と変動費を算出する方法です。
メリット
- 計算がシンプル
- 導入が容易
デメリット
- 2点のデータしか使わないため精度が低い
- 外れ値の影響を受けやすい
スキャッター・チャート法
実績データをグラフ化し、目分量で直線を引いて固定費と変動費を推定する方法です。
メリット
- 直感的で理解しやすい
- 視覚的に操業度とコストの関係を把握できる
デメリット
- 精度が低く、担当者の主観に左右される
最小自乗法
最小自乗法は、過去の全データを使って誤差が最小になる直線を計算で導き出す方法です。
メリット
- 全データを反映するため精度が高い
- 統計的な裏付けがある
デメリット
- 計算が複雑
- 専門知識が必要



ExcelやPythonを用いて回帰分析を行い、固定費と変動費を数値化するケースで使われます。
勘定科目精査法
勘定科目ごとに、固定費か変動費かを判断して分類する方法です。
メリット
- 財務会計データをそのまま活用できる
- 分類作業がシンプル
デメリット
- 担当者の判断に依存する
- 業種によって分類基準が異なる



「水道光熱費」を固定費か変動費か判断する際、製造業では操業度に応じて変動費として扱う一方、オフィス業務では固定費とする場合があります。
原価分解の選び方


原価分解の手法は、目的や状況によって使い分ける必要があります。
代表的な手法の比較表
| 方法 | データの必要性 | 精度 | 導入のしやすさ | 主な用途 |
| IE法 | 実績不要 | 高い(条件次第) | 難しい | 新製品のコスト予測 |
| 高低点法 | 過去データ2点 | 低い | 簡単 | 簡易的な原価分析 |
| スキャッター・チャート法 | 過去データ複数 | 中程度 | 普通 | 視覚的な把握 |
| 最小自乗法 | 過去データ多数 | 高い | 難しい | 精度重視の分析 |
| 勘定科目精査法 | 財務データ | 中程度 | 簡単 | 実務的な分類 |
原価分解の実務活用例
製造業での原価管理
- IE法を使って新製品の原価を予測し、価格設定や利益計画に活用。
サービス業での費用分析
- 勘定科目精査法を使って、固定費と変動費を分類し、損益分岐点分析に活用。
経営判断におけるCVP分析
- 最小自乗法で精度の高い原価分解を行い、売上目標やコスト削減施策の立案に活用。
まとめ
本記事では、原価分解の基本と代表的な手法について解説しました。
原価分解は、企業がコスト構造を正しく理解し、意思決定や戦略立案に活かすための重要な手法です。
IE法・最小自乗法・勘定科目精査法など、目的に応じて適切な手法を選ぶことで、より精度の高い原価管理が可能になります。



企業の目的や利用シーンに応じて、適切な手法を選択することが大切です。
原価分解をうまく活用すれば、より正確なコスト管理や意思決定に役立ちます。