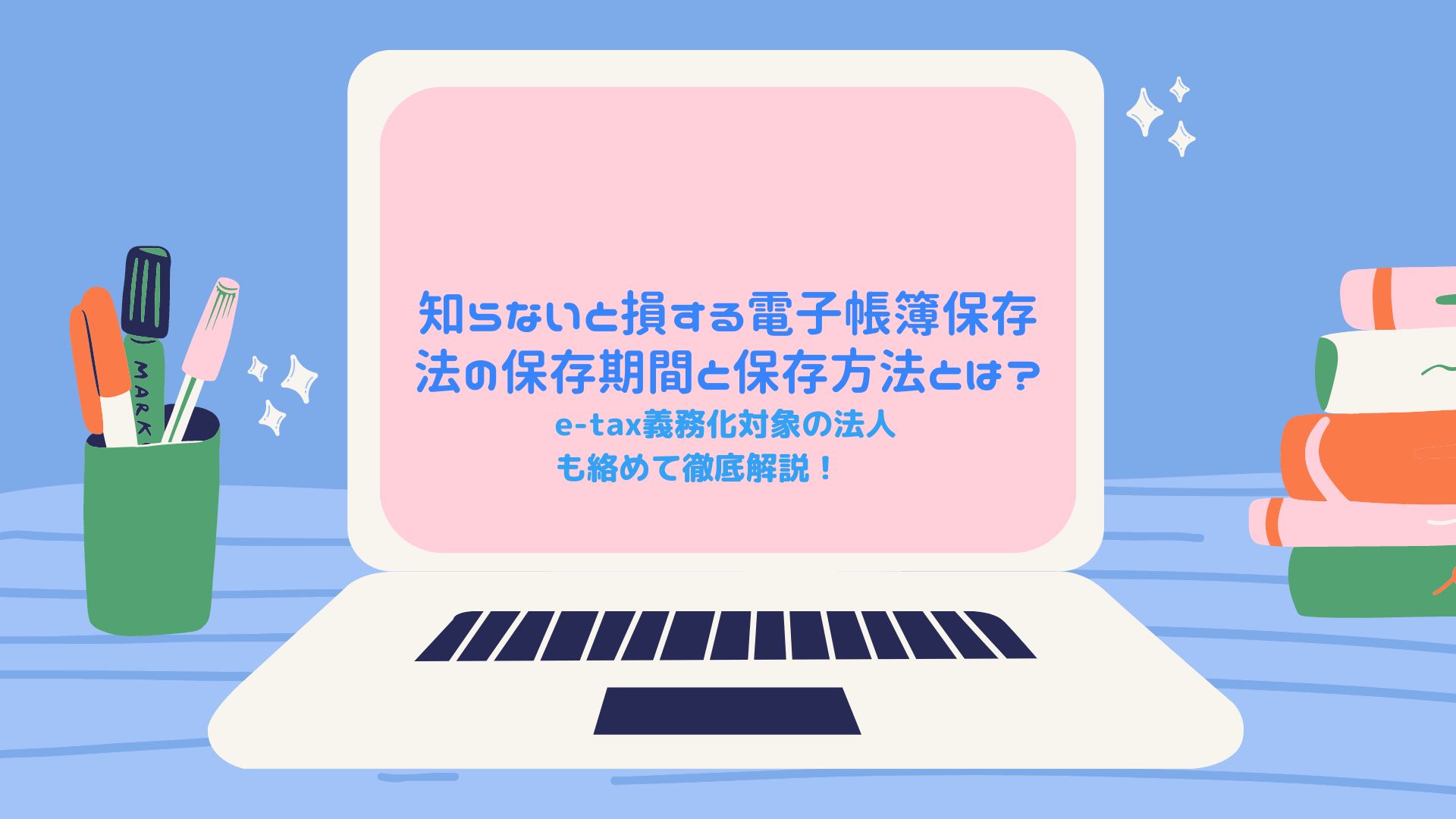電子帳簿保存法が改正され、厳格だった要件が緩和されたことから、多くの企業が対応を進めています。

法対応をこれから始める企業にとっては、保存期間や保存方法についての理解が課題となっています。
この記事では、「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」について詳しく解説します。
- 電子帳簿保存法の保存期間はどれくらいなのか?
- 電子帳簿の保存方法にはどのような要件があるのか?
- e-Taxを利用しなければならない法人とは?
最後まで読むことで、電子帳簿保存法の基本的な知識が身につき、スムーズな対応が可能になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿の保存期間
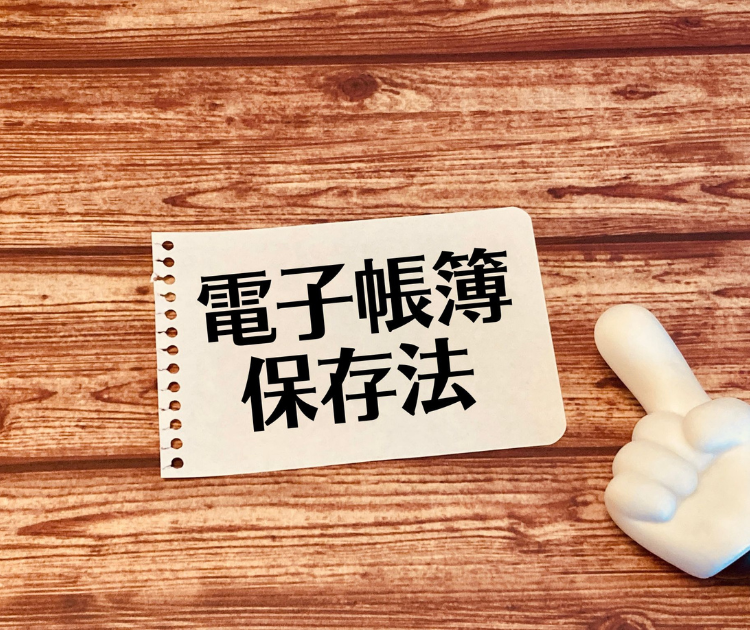
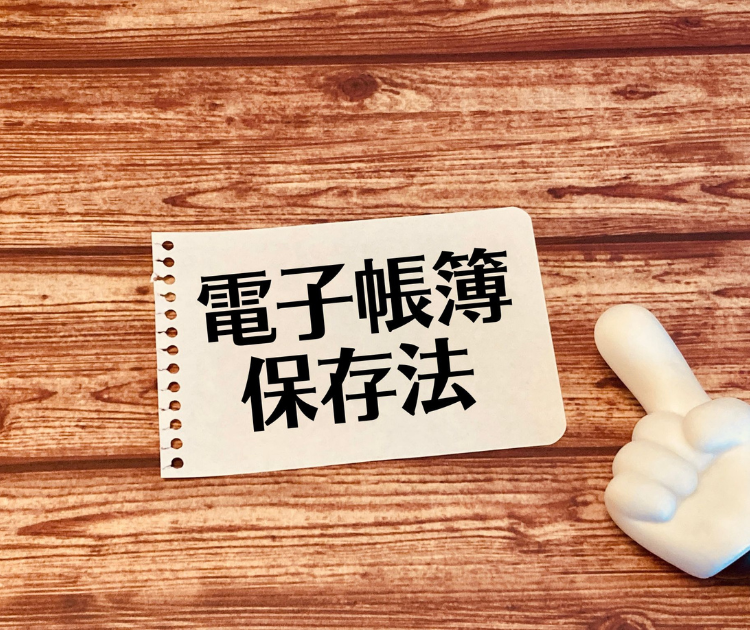
電子帳簿保存法は、従来紙で保存することが義務付けられていた帳簿書類を、電子データとして保存することを認める法律です。



企業は紙の書類を電子化し、保管コストの削減や業務の効率化を図ることができます。
電子帳簿保存法の対象となる帳簿書類には、以下のようなものがあります。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 領収書・請求書(スキャナ保存)



これらの書類を電子保存することで、ペーパーレス化の推進が可能になります。
電子帳簿保存法自体には保存期間の規定はありませんが、法人税法などの関連法令に基づき、以下のように定められています。
法人税法における保存期間
国税関係帳簿(総勘定元帳・仕訳帳など)
- 7年間(法人税の申告期限から起算)
重要書類(請求書・領収書など)
- 7年間(法人税法に基づく)



欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間保存が必要です。
消費税法における保存期間
消費税の仕入税額控除に関わる帳簿・請求書
- 7年間(消費税法に基づく)
国税関係帳簿や請求書・領収書の保存期間は基本的に7年間と考えておくと良いでしょう。
電子帳簿の保存方法
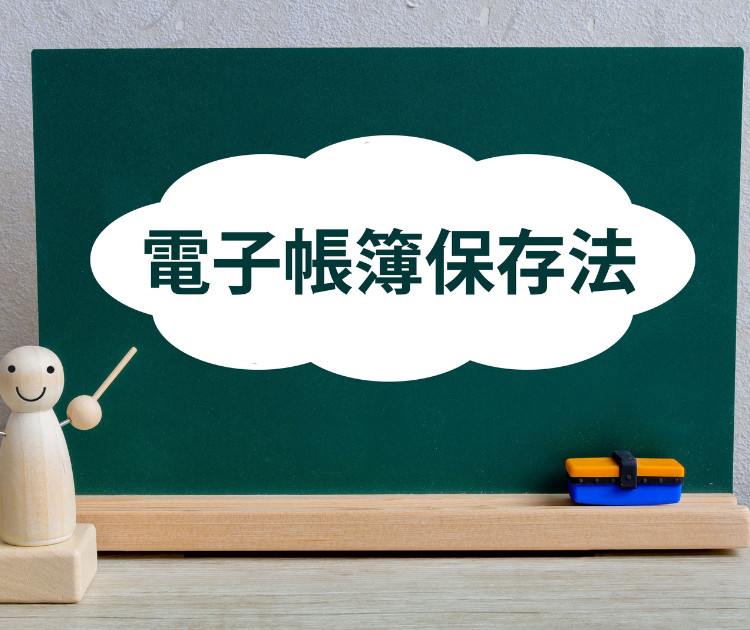
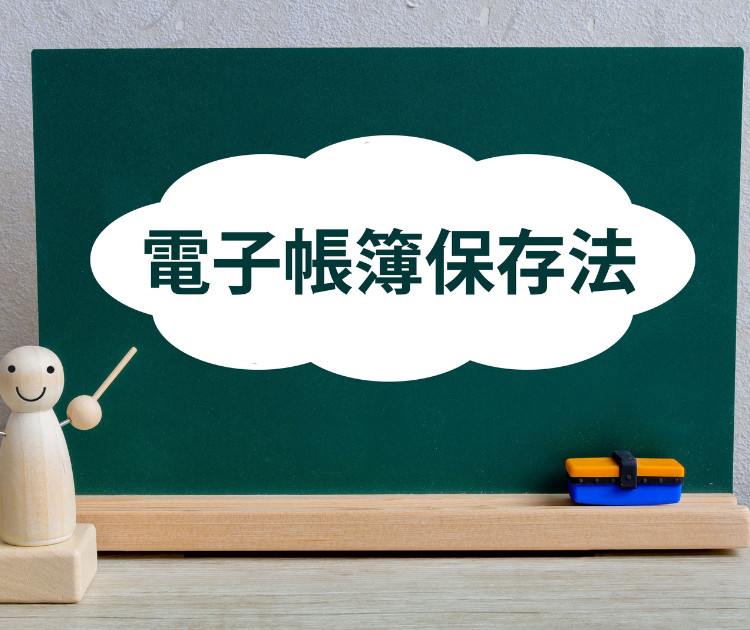
電子帳簿保存法に基づく保存方法には、以下の要件を満たす必要があります。
電磁的記録の保存環境の整備
電子帳簿を適切に保存するために、以下の設備が必要です。
- 電子計算機(コンピューター)
- プログラム(会計ソフトなど)
- ディスプレイ(データの閲覧が可能な画面)
- プリンター(必要に応じて帳簿を出力可能)
見読性の確保
税務調査時にデータを画面表示または紙で出力できることが求められます。
そのため、電子データは適切に管理し、税務職員の求めに応じて即座に確認できる環境を整えておく必要があります。
検索機能の確保
電子帳簿保存法では、保存したデータに対して以下の条件を満たす検索機能が求められます。
- 取引年月日、取引金額、取引先名で検索できること
- 複数の条件を組み合わせた検索が可能であること
- 日付や金額の範囲指定による検索が可能であること
真実性の確保
改ざんや削除を防ぐため、以下のいずれかの方法で電子データの真正性を確保する必要があります。
- タイムスタンプの付与
- 訂正・削除履歴の記録
- システムやソフトウェアでの適切な管理
e-tax義務化の対象法人
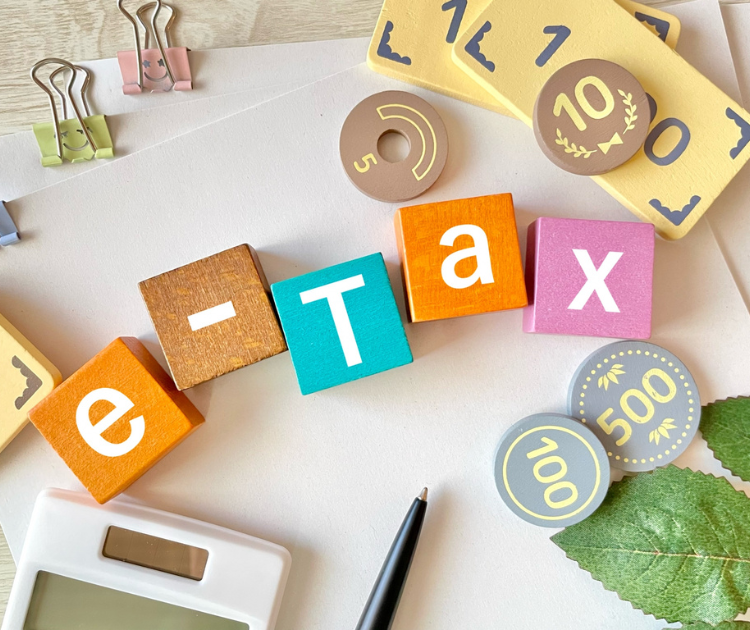
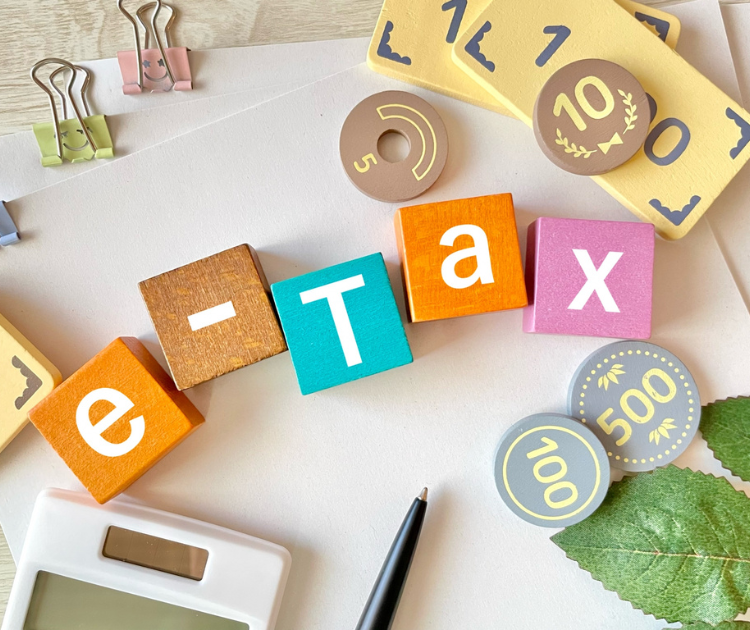
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、法人税や消費税などの申告・納税をオンラインで行うシステムです。
電子帳簿保存法とは異なる制度ですが、以下の法人にはe-Taxの利用が義務付けられています。
- 資本金1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
- 国、地方公共団体などの消費税固有の納税者
e-Taxと電子帳簿保存法は別々の制度であり、電子帳簿保存法に対応していてもe-Taxの利用が義務付けられるわけではありません。



電子帳簿保存法に対応していない企業であっても、e-Taxの義務がある場合は、オンラインでの申告が必要となります。
逆に、電子帳簿保存法に対応していても、e-Taxの義務がない企業は紙での申告も可能です。
まとめ
今回は「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」について詳しく解説しました。
- 電子帳簿保存法の保存期間は法人税法に基づき原則7年間
- 保存方法は電子データの見読性と検索機能の確保が必須
- e-Taxの義務がある法人は資本金1億円超の法人などが対象
- 電子帳簿保存法とe-Taxは別の制度なので混同しないこと



電子帳簿保存法に対応することで、業務の効率化やペーパーレス化が進みます。
これから対応を検討している企業の実務担当者は、しっかりと準備を進めていきましょう。
今後も電子帳簿保存法や税務関連の情報を発信していきますので、ぜひチェックしてください!